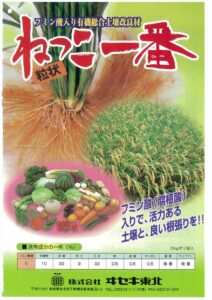お米作りは稲刈りの直後から始まる
井関農機の創業者・井関邦三郎は体が弱かったそうです。彼は「農家を過酷な労働から解放したい」と考え、昭和期まで牛馬の力を用いていた農作業を機械化しました。その口癖は「人からほめられるような、ええもんをつくるんやぞ」というもの。日本のお米作りがこういった無数の方たちの力によって形作られたのだと感じ入ります。
そんな井関農機さんならば、当然、お米作りの作業を1から88までご存じのはず。そこで筆者が茨城県つくばみらい市にある同社の「夢ある農業総合研究所」を訪ねてきました。
【写真】
お答えいただいた、井関農機「夢ある農業ソリューション推進部」副部長の川嶋桂さん(左)と同部主任の山本玄棋(右)さん「農業は気候や地質の影響を受けるので“関東のやり方が北海道でも同じ”とはなりません。あくまで一般論ですが……(山本さん)」と教えてくれました。
「まずは苗作りでしょうか?」と伺うと、こんな答えが返ってきます。
「実を言うとお米作りは稲刈りの直後から始まっているんです。苗を作る前に、土作りをするんですね」(山本さん)
88の手間、1つめは「人間だけではできないこと」
川嶋さんが話します。
「田畑の土壌には、粘土鉱物(砂や壌土粘土などの粒子)と有機物(動・植物の遺体が分解されたもの)と空気と水が混ざっています。土壌は表面10~30cmくらいしかなく、そこから下には、踏み固められ、鉱物の割合が高く、水が染みこみにくい“不透水層”があり、植物は根を張ることができません。」
川嶋さんは取材の終盤で「植物が育つ土壌は地球の表面にたった数十cmしかありません。豊かな土壌は貴重な財産なのです」ともおっしゃいました。地球をリンゴにたとえれば、植物が育つ土壌は皮よりも薄いのです。山本さんが話を継ぎます。
「とはいえ、不透水層も大切な役割を持っています。田畑の下、深くまで空気や水が混ざりやすい土壌だったら、田は底なし沼のようになって農作業はできないでしょう。また、せっかく田に水をはっても、水が地下に抜けてなくなってしまいます」
では、そんな土をどうするのでしょうか。
「まず、お米を収穫した直後に“すき込み”という作業から始める場合が多いですね。稲の藁は栄養になるので、収穫後、これを砕いて土の中にすき込んでいくんです」(山本さん)
皆さんは「炭素循環」という言葉をご存じでしょうか? 植物は光合成を行い、二酸化炭素(CO2)を取り入れ、酸素(O2)を出しながら成長します。「CO2(二酸化炭素)-O2(酸素)=C(炭素)」、すなわち、植物は茎も実も主成分は炭素。もちろん稲も、藁やお米の主成分は炭素なのです。
一方、人間を含む生き物は、動いたり考えたりするため、食物として取り入れた炭素に酸素を反応させ、エネルギーにしています。呼吸で酸素(02)を取り入れ、これに不要な炭素(C)をくっつけ、二酸化炭素(CO2)にしてはき出すイメージです。そして、生き物から排出された二酸化炭素は大気中をただよい、光合成によって再び植物の茎や葉や実(炭素)と酸素になります。
そう、炭素は植物、生物、大気、植物……とぐるぐるまわっているんです。そして、炭素と同じように植物に含まれる窒素やそのほかの成分も植物の栄養に再利用されるのです。
「ただし、そのままでは植物の栄養にはなりにくいんですね。植物に再利用されるには、細かく分解される必要があるんです。(川嶋さん)」
イメージとしては植物体がボロボロになって、腐っていく過程が必要になります。
「植物体を腐敗させるには微生物の力が不可欠です。微生物が植物体を分解することで、植物が取り入れられる形状になるんです。だから“すき込み”の時にはしばしば、微生物の活動を活発にする『土壌改良材』を入れ、わら等の腐植を促進することがあります(山本さん)」
これが土壌改良材「ねっこ一番」のパンフレット。名前がかっこいい!
なんと88の手間の1つめには、人間ができないことも含まれていたのです。
“よい土壌”は太古から引き継いだ財産
ちなみに窒素も植物と空気と生き物の間をぐるぐるとまわっています(窒素循環)。そして窒素も、植物の肥料になり、生き物の体ではタンパク質になるなど、炭素と同じくらい重要な役割を果たしています。川嶋さんが話します。
「土壌づくりをする際には、そのバランスが大切です。炭素と窒素と空気と水、その量を育てる植物に合わせて変えていくんです。ちなみに、昔は農業者の勘と経験に頼っていましたが、今は土の状態を分析し、データに従ってお米を育てる方が増えています。我々もこのデータを積極的に農業者の方に伝えていますよ。最先端の農業は情報産業の側面も持っているんです」
これでようやく1つめの手間が終わり、2つめが始まります。
「すき込みの次に、深く耕すと書いて“深耕(しんこう)”と呼ばれる作業を行います。先にお伝えしたとおり、土壌は地面表面の10~30センチにあって作物を育みます。しかし、農作業で土壌が踏み固められるなどして、これが不透水層に変わっていってしまうことがあるんです。稲の根は不透水層の中にまでは入っていきませんから、土壌が薄いと、根が育ちにくくなり、結果として稲が弱くなります。そこで土を深く耕し、不透水層をほぐすようにして根の張りやすい土壌に変えていくんです(山本さん)」
次が3つめ。深耕を終えたら“耕耘(こううん)”を行う場合があります。不透水層をほぐしても、土のかたまりが残ってしまいます。これは水や、栄養素を微生物が分解するために必要な空気や水を含みにくいので、細かく砕く必要があるのです。
次が4つめ。このあたりで「畦塗り(あぜぬり)」を行う場合があります。田んぼの周囲のあぜ(あぜ道の「あぜ」)に土を塗りつけ、割れ目や穴をふさぐ作業です。これをしないと、田の水が漏れ、肥料の効果も下がってしまいます。
そして、次に5つめの田に水を張る作業があり、次が6つめの“代掻き(しろかき)”です。
「この作業は、見たことがある方も多いかもしれません。代掻きをする光景が、ニュースで“いよいよ田植えが始まります”と報道されることが多いんですね(山本さん)」
春、田植えを行う前、田んぼに水をはった状態で土をかき混ぜ、細かく砕き土の表面を平らにしていく作業です。これによって苗が植えやすくなり、植えた苗がムラなく成長します。また、かき混ぜて雑草の種を深く埋め込むことによって、雑草の発芽を抑える効果もあります。
というわけで、代掻きが終われば次は田植え。この6つでようやく土作りが完了した、というわけです。
ところで川嶋さん、この複雑な土作り、いったいどう始まったのでしょうか?
「それぞれの国・地域の方が試行錯誤を繰り返してきたんでしょうね。米作りには“これが正解”というものはなく、その土地土地で少しずつ異なりますし」
“試行錯誤”――シンプルで、重い一言です。熱帯性の植物である稲は、水が豊かな東南アジア、中国南部を経て日本に伝わってきたと考えられています。そしてこの間、膨大な数の人間たちが、生きるために道具を進化させ、雑草と戦い、今の米作りへと進化させてきたのです。
【まとめ】
お米をつくる手間、最初は土作りから始まることがわかりました。次回は田植えの前に行う苗作りの話をします。
井関農機様のトラクターの写真
井関農機の「ロボットトラクタ」。GNSS(全球測位衛星システム)を活用し、自動操舵技術「ISEKI DREAM PILOT」の技術により、オペレーターが監視・遠隔操作すれば無人作業が可能。不慣れな農業者でも扱えるため、農作業の習熟にかける時間的コストを大幅に削減できる。